大切な方が亡くなったという悲しい知らせを受けた時、私たちは故人への感謝と、ご遺族への心からのお悔やみを伝えるために、お香典を用意します💴
しかし、いざ香典袋の表書きを書こうとした時、ふと手が止まるかもしれません🤔
「香典って、薄い墨で書くって聞いたけど、本当かな?」
「なぜ薄墨なんだろう?」
「どうやって書けばいいの?」
「もし薄墨がなかったらどうすればいいんだろう…?」
日常ではほとんど使うことのない「薄墨(うすずみ)」。
その独特の濃さには、日本の伝統的な弔事(ちょうじ)における深い意味と、故人やご遺族への細やかな配慮が込められています🕊️
しかし、その意味を知らずに、ただ「マナーだから」と形だけを真似しようとすると、かえって戸惑ってしまうかもしれません。
というわけで今回は、香典袋を用意する際に使われる「薄墨」について調査!
薄墨を使う理由や正しい書き方、手元に薄墨がなかった際の対処法などをご紹介していきます。
香典は「薄墨」で書くのがマナーとされている理由は?
香典を薄墨で書く習慣は、日本の伝統的な作法の一つであり、そこには故人やご遺族への深い心遣いが込められています。
主な理由は以下のようなものでした。
「悲しみの涙」で墨が薄まった表現😢💧✒️
今回の調査の結果、これが最も広く知られている理由でした。
「大切な人を失った悲しみで涙があふれ、墨をする手元が震え、涙が墨に落ちて薄まってしまった」という心情を表現しているとされます。
故人を悼む深い悲しみを象徴する意味合いが込められています🕊️🪄
「突然の訃報」で墨をする時間もなかった、という表現⏳❌
「あまりにも突然の訃報で、動揺して墨をする時間もなかった」
「急いで駆けつけたため、墨をする暇がなかった」
という状況を表している、とも言われていました。
故人の死を予期していなかった突然の出来事であることへの驚きや動揺を示す意味合いがあります。
悲しみを分かち合う気持ち💖🙏
薄い墨色は、沈痛な空気感や悲しみを表現し、ご遺族の悲しみに寄り添い、その気持ちを分かち合おうとする参列者の姿勢を示します。
他の慶事と区別するため
結婚式などの慶事(お祝い事)では、濃い墨でくっきりと文字を書きます✒️
これに対し、お葬式という弔事では薄墨を用いることで、喜びの場と悲しみの場とを明確に区別する意味合いもありました。
香典で薄墨を使うことは単なる形式ではなく、故人への哀悼の気持ちと、ご遺族への最大限の配慮を表現する、日本の美しい心遣いですね。
【基本の書き方】香典袋の表書きはこう書く!
では実際に香典袋に薄墨で表書きを書く際の基本的な方法を確認していきます👆
書くべき事
香典袋の表書きには、以下の三つの情報を記載するのが基本です。
- 表書き(おもてがき):「御霊前」「御仏前」など、宗教・宗派に応じた表書きを中央上部に書きます。
- 氏名:中央下部に、表書きよりもやや小さめの文字でフルネームを書きます。連名の場合は、右から目上の順に書きます。
- 金額:中袋(または中包み)の表に、旧字体(大字)の漢数字で金額を書きます。
- 住所・氏名:中袋(または中包み)の裏に、住所と氏名を記載します。
書く位置
- 表書き(御霊前など):袋の中央上部に、バランス良く書きます。
- 氏名:表書きの真下、袋の中央下部に書きます。
筆記用具は「薄墨筆ペン」が便利✒️
現在は、筆と墨を硯でする機会はほとんどありません。
そのため、文具店やコンビニエンスストアなどで手軽に手に入る「薄墨筆ペン」を用意するのが便利です。
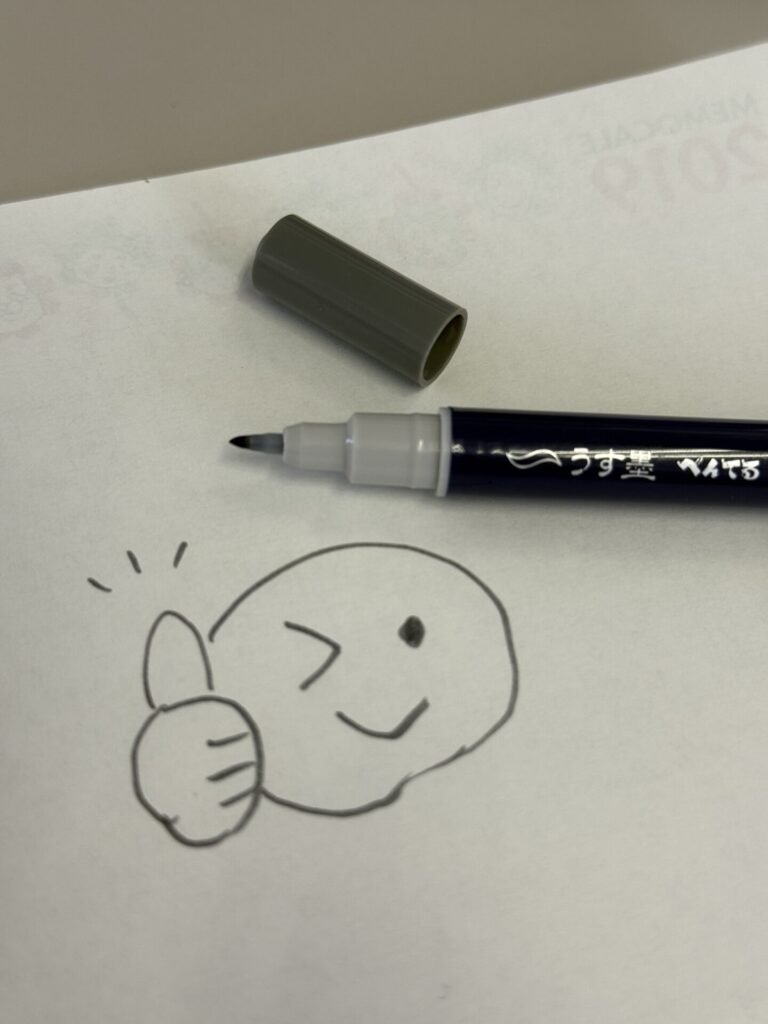 ぺんてる慶弔サインペン(速乾)
ぺんてる慶弔サインペン(速乾)
わたしは写真の「ぺんてるうす墨慶弔サインペン」をペンケースにいつも入れています。筆先が中細で、字がヘタなわたしでも使いやすいです。うす墨と濃い黒の2色で便利です。
薄い灰色がかった墨色が出るように調整されています。
文字の濃さ:読みやすい程度に
薄墨といっても、文字が読めないほど薄く書くのは失礼にあたります。
故人やご遺族への配慮として、相手が読める程度の濃さで、丁寧に書くことを心がけましょう。
筆圧や筆ペンのインクの出具合を調整しながら、読みやすい濃さを目指します。
もし薄墨がなければどうする?現代の対応と代替策
「急な訃報で、薄墨筆ペンが手元にない…」
そんな時、どうすれば良いのでしょうか?
無理に探し回る必要はありません。
現代の葬儀マナーでは、柔軟な対応が許容される場合も増えています。
「濃い墨」でも許される場合✒️
近年では、薄墨の筆記具が手元にない場合や、急な参列の場合は、普通の濃い墨(黒いボールペンやサインペン、濃い筆ペンなど)で書いてもマナー違反とはされないことが増えています。
特に、通夜や告別式が自宅ではなく葬儀会館で行われる場合や、参列者が多い場合など、形式よりも気持ちが重視される傾向にあるようです。
状況を考慮する (急な参列など) 🚨
突然の訃報で、薄墨を用意する時間がない、あるいは遠方からの急な参列で準備が間に合わない、といったやむを得ない事情がある場合は、濃い墨で書いても問題ありません💁♀️
薄墨を用意できない時の代替策 代替ペン 🖊️
正式な代替策ではありませんが、どうしても気になる場合は、黒い筆ペンで書き、その文字を乾く前にティッシュなどで軽く押さえてインクを薄めるという方法もあります。
ただし、滲み具合の調整が難しいので、事前に試すことをお勧めします。
一番大切なのは、故人やご遺族への「心からの弔意」です。
マナーに囚われすぎて、焦ったり、間に合わなかったりする方が、かえって失礼になることもあるので、よき塩梅で取り入れていきましょうね。
香典を渡す際の全体的なマナーと注意点🤝📜
香典を準備する際は、薄墨の濃淡だけではなく、渡す時の全体的な作法も確認しておきましょう。
香典の金額相場
故人との関係性(親族、友人、仕事関係など)によって香典の金額相場は異なります。
宮城県での香典の相場は、故人との関係性や年齢、地域の慣習によって異なりますが、ネット上で調べた結果をまとめると、一般的には以下のようになっていました。
一般参列者:三千円、五千円
両親:三万円、五万円、十万円
兄弟姉妹:一万円、三万円、五万円
祖父母:一万円、三万円
勤務先の家族:五千円
上司:一万円
友人・知人:三千円、五千円、一万円
ご近所:三千円、五千円
香典の金額は、故人との関係性や自身の年齢、地域によって異なります。迷った場合は、親族や他の参列者と相談して決めるのが良いでしょう。香典を包む際は、金額だけでなく、故人への哀悼の気持ちを込めることが大切です。
一般的に、4や9など「死」「苦」を連想させる数字は避けるのがマナーです。また、新札は「前もって準備していた」という意味合いになるため、不幸を予期していたような印象を与えかねません。
新札しかない場合は、一度折り目をつけてから包むのがマナーとされているようです。
袱紗(ふくさ)を持参する
 袱紗(ふくさ)
袱紗(ふくさ)
香典袋は、そのまま手で持ち歩かず、必ず袱紗に包んで持参するのがマナーです。
袱紗(ふくさ)は、お香典が汚れたり折れたりするのを防ぎ、また弔事に対する敬意を示す意味合いがあります。
弔事用の地味な色(紺、緑、紫など)を選ぶのが無難です。
まとめ:薄墨は「故人への哀悼」と「ご遺族への配慮」の証
香典を薄墨で書くという作法は、故人を深く悼む気持ち、そしてご遺族の悲しみに寄り添う細やかな配慮が形になったものです。
現代では、すべての場面で厳密に薄墨が求められるわけではありませんが、その背景にある「悲しみの表現」という意味を知ることで、故人への敬意とご遺族への思いやりが、より深く伝わります。
あなたの心遣いが、悲しみに暮れるご遺族の心の支えになるかもしれません💐🕊️🙏
葬儀に参列する際は、今回ご紹介した香典の書き方などを参考にしてみてくださいね。
少しでも不安がある方は、事前に確認しておくと安心ですね。
みやぎ生協の葬祭「プリエ」では、葬儀のご相談や準備についてもサポートしております。
気になることがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
この記事が、皆様の葬儀に関する疑問や不安を解消し、安心して故人を送るための一助となれば幸いです🌸
葬儀のことでお困りの際は、プリエ案内センターにご相談くださいませ!
プリエでは、「税理士法人」、「行政書士法人」、「相続専門不動産」、「特定非営利活動法人」の4つの専門機関が連携。
相続に関する悩みに対応する「みらいえ相続グループ」と提携して組合員の皆さんのお悩み解決を手助けもしています。
LINE公式アカウント、はじめました!
お友だち募集中です。
